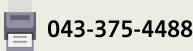cbaニュース
第233・234合併号 「HD 伝送実現へ向けIP キャスティングがチャレンジ開始」
[2005.08.08号]
しかし、暑い。夏だから、当然だと言えば当然だが、今年は昨年より暑い気がする。昨年までは、昼間、仕事部屋に入って、汗をだらだらかきながら原稿を書いていても、ぼーっとすることはなかったが、今年はどうも、もわっとして、頭がぼーっとしてくる。クーラーはあまり
好きでないので、仕事部屋には入れていない。ぼーっとするのは、窓を開けても、風がないせいもあるだろう。しかし、たまに熱風が吹き込ん
でくることもあり、余計にもわっとして、どうも考えがまとまらない。言葉が降りてこない、というか。夕方、カミナリが鳴って、おしめりでもあれば、いくらか涼しくなって、夜が過ごしやすいのだが、そんなカミナリはここでは鳴らない。
子供の頃を過ごした栃木県南部の都市、栃木市周辺(というか栃木県一体がカミナリ銀座であちらこちらでカミナリが鳴ったが)では、いつも夕方になると、カミナリが鳴って一雨降った。1時間ほどで、雨が上がると、いくらか夏の暑さを忘れさせてくれた。路地では、浴衣姿の子供達が、花火を楽しんでいて、スイカはつきものだった。
そういえば、今年は、6 月頭から8 月の第1週までに、スイカを丸ごと9つ買って来て、スタッフともども平らげた。千葉の富里に始まり、同じく千葉の八街、鳥取の大栄町(平成17 年10 月
1日に北条町と合併して、「北栄町」が誕生する)、神奈川県の三浦、新潟などの丸ごとスイカを買ってくる。このスイカに包丁を入れると、ピシッという音がして、さながら桃太郎でも出てきそうな感じを抱かせる。出て来るのは、真っ赤なスイカの中身だが、その二つに割れたスイカの断面の表情にもいろいろあって、これがまた楽しい。たまに、「これは」というものがあると、デジカメを持ち出して、まな板の上の二つに割れたスイカの表情を撮ったりする。
割れた片方をラップに包み、冷蔵庫へ。もう一方をまた半分に切り、片方を冷蔵庫へ。残った4分の1をヨコにして、端から縦に包丁を入れ、三角形の山の形をしたスライスを大皿の上に並べる。端っこを一口頬張る。それほど冷えていないスイカだが、常温(お酒みたいですが)の甘味には、なんともいえないものがある。漂うスイカの匂いに、パソコンに向かっていたスタッフも「いい匂い」と口を揃える。しばらくは、午後の休憩だ。
暑い部屋の中で熱中症になってはまずいので、水分補給に心掛けるが、冷たい水や冷たいお茶ばかりでは飽きるので、合間合間にスイカを一切れ二切れと口に入れる。だから、3L とか2L のスイカの大玉が1週間もすると消えてなくなる。そしてまた買ってくる。例年、一夏で6~7個を食べているので、今年の夏はやっぱり暑く、体が水分を欲しがっているのだと思う。95 年の7 月に、北京のケーブルショーを取材に行った時、「北京の夏は暑く、庶民が水分を求
めて、スイカを食べ、その量は、スイカの皮がゴミ問題になるほどだ」と聞いたことがある。どうも今年は、軽く、もう2~3個いきそうだ。
しかし、来年の夏も、そして再来年の夏も、もっと暑くなったら、どうなってしまうのだろう。テレビのニュース番組のインタビューに答えた街ゆくおばさんは、「体温より暑いんですものね~」といっていた。これ以上暑くなるようだったら、昼間は、日陰の涼しいところで、ゴロ寝するしかないだろうな。東南アジアが、そのまま日本にやってくるみたいなものだ。そうなったら、今のスイカの産地も北上するのだろうな。農作物の産地がかわってくる。う~ん。日本の食糧は大丈夫だろうか。これは、杞憂だ、なんていってられない。
自ら変わって(農作物を自分で作るとか…)、食べるものも変えていく(粗食にするとか…)、
というようなことも必要かもしれない。
ああ、大事なことを思い出した。その前に鍬を持つ体力をつけなければいけない。(い)
【目次】
◆1. 巻頭言「いよいよ地上デジタル放送普及促進のために、IP、衛星を投入」(p3)
◆2. (平成16 年諮問第8 号)第2次中間答申の概要(p4)
「地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割」
~2011 年全面移行ミッションの確実な実現に向けて~
◆3. 総務大臣の諮問『平成16年諮問第8号に対する情報通信審議会第2次中間答申』に
係る問題点(案)――日本ケーブルテレビ連盟(p6)
◆4. 第2次中間答申に関する日本ケーブルテレビ連盟記者会見(抄録) (p8)
◆5. ~JCTA トップセミナー基調講演録~「ケーブルテレビ業界の発展に向けて」(p11)
総務省地域放送課技術企画官田口和博氏
1.「メーカーとのWin Win」の関係作り(p12)
≪市場に魅力がなければ、いつかメーカーは撤退するだろう≫
2.「番組供給事業者とのWin Win」の関係作り(p13)
≪視聴者が見たいと思っている番組とケーブルが提供している番組の間のかい離が知ら
ない間に進んでいるのではないか≫
3.「ケーブルテレビの産業化」(p15)
≪プラットホームを提供して稼いでいくことが多分これから必要になってくるだろう≫
4.「状況は変わった」(p15)
≪自分達の強み弱みを踏まえ戦略を立てていくことがケーブル業界に今求められている≫
5.「戦略を確立する」(p16)
≪業界としてのアピールをするときに、バラバラでは誰も相手にしてくれない≫
6.「ポジションを明確化する」(p17)
≪加入者からすれば同じサービスが同じ値段で提供されるのであれば、それはケーブルテ
レビであろうともNTT であろうともかまわないといわれる可能性が高い≫
7.「弱点を克服してポテンシャルを生かす」(p18)
≪ケーブルは自分達の持っているポテンシャルを十分に使い切っていないのではないか≫
8.「ユビキタス時代をどう捉えるか」(p20)
≪人間自身には孤独感というのがあり、一種の所属意識と帰属意識が欲しくなってくる≫
9.「地域と共に発展する」(p21)
≪地域の核になれるかどうかが、ケーブルの地域密着というものの重要な部分ではないか≫
◆6. ジュピターテレコムの現状と2005 年下期に向けた展開(p23)
<インタビュー>加藤徹取締役事業開発統轄部長に聞く
【デジタル加入世帯は順調に増加】(p23)
≪テレビ契約のお客様にインターネットや電話をつけていただくバンドル戦略を展開≫
【全国のJ:COM エリアでVOD サービスを展開】(p24)
≪オン・デマンドは、実際に使ってみてもらわないとイメージがわかないサービスですね≫
【サービス加入数は、1.7 を超えた】(p26)
≪電話は、今も加入率がどんどん高くなっていて、インターネットを抜いているくらいで、我々の
なかでは非常に競争力の高いサービスだと思っています≫
【プライマリー電話サービスの卸売りを展開】(p28)
≪電話は重要なビジネスなので、局としてオペレーションできる体制にすることも大切≫
【デジタル加入の増加で問い合わせが急増】(p29)
≪特にインストールなどの技術力もアップさせる。もう少し、お客様と接する人を増やしていく≫
【ローカルに根ざした地道なプロモーション活動を展開】(p31)
≪お客様と直接販売がセールスの基本で、一人一人ていねいに説明して加入してもらうというこ
とに重きを置いている≫
【集合住宅で高速インターネットサービスを実現するc.LINK も導入】(p32)
≪FTTH を引いて、かつ集合住宅棟内はc.LINK でやれば、多分、VDSL よりはいいパフォーマン
スが出せると思う≫
【HD にも積極的に対応】(p32)
≪東名阪のネットワークを使ってケーブル独自のHD チャンネルも展開したい≫
◆7. JC-HITS 新規採用ケーブルテレビ局(p33)
◆8. I-HITS 新規採用ケーブルテレビ局(p35)
| 次号へ | cbaニュース一覧 | 前号へ |