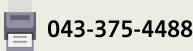cbaニュース
第257号 「デジタル家電が街に家庭に溢れる時代。消費者に安心・安全・信頼を誰が提供するのか」
[2006.07.25号]
この間もあるセミナーで、カチンときてしまいました。言っておきますが、私は、そんなにカチンとくる方ではありません。もともとは短気かもしれませんが、それほど、怒りません。でも、たまに怒る。
始まって5分。講演者は、「日本のケーブルテレビの普及は、33%くらいになっていますね。でも、米国と比べると、ケーブルテレビの人には申し訳ないですが、日本のケーブルテレビは垂れ流しばっかりですね」といってしまいました。
思わず、「なんだ。こいつもか!」とカチンと来て、講演後の質問の時を待って、
「垂れ流しとは、何をもっていっているのか?」
「現在の日本の状況でいえば、垂れ流しばかりとはいえない、と思うが」
「それに、垂れ流しであろうと、テレビを見せる、という基本的な機能を顧客に提供しているわけであって、それはいけないわけでも何でもない。それを経営している人もいるし、そこで働いている人もいるし、その給料で家族を養っている人だって多い。全国でいえば、ケーブルテレビの雇用はけっこう大きい。それを貴方ほどの方が、『垂れ流しばかりだ』といいきるのは、いかがなものか?」といってやろうと思いましたが、まあ、今回は、大人になって、
Q:「米国のSBCやベライゾンなどがIPTVを始めた地域は、金持ちが多い地域なのか、自分たちがケーブルより強い地域なのか、それともケーブルが弱い地域なのか?」
A:「SBCは、どこどこ(よく聞こえなかった)、ベライゾンは、テキサスで始めて、次はニューヨークですね」
Q:「IPTVが始まって、IPTVはケーブルの市場をどれくらい食えると思うか?それはどれくらいの期間になのか?」
A:「シェアですか? わからないですね」(何か、彼なりの見解をいって欲しかった)
Q:「SBCやベライゾンのIPTVについて、ウオール街はどうみているのか?」
A:「これもわからないですね。様子見というというところではないですか」
(う~ん。やっぱり、この方、通信系だから、映像ビジネスは、それほど深く追ってないんだろうなあ。それはそれで仕方がないが…)というような質問に留めました。
終わってから、名刺を交換しにいったら、わりとドングリ目で、悪気はないのだろうな、とは思いました。が、私の怒りのポイントをいいますと、講演者として、(何事もそうだが)「日本のケーブルテレビは…」などと、『全否定』をしてしまうのはおかしい。会場の人に手を挙げさせて、ケーブルテレビが2社、関係者が3社、あとは通信系が中心だったので、このように発言したのかどうかわからないですが、通信ジャーナリストだから、という理由ではなく、よっぽどでない限り、「ある物事を全否定する発言」は、講演者は行なってはいけないのではないかと私は思う。
だいたい、世の中に、全否定できる、事実などは、めったに、ありはしない。
だから、「ケーブルテレビの方には、申し訳ないですけど…」と断っての発言であっても、「全否定」はおかしい。もし、否定的なことをいうのであったら、「地上波やBS、CSの再送信が中心で、まだ、VODなどはそれほど普及していない。そういう点で、日本のケーブルは、まだまだだと思う」くらいに言っておけば、私が(参加した他のケーブル関係者の方もだが)怒ることもないだろうに。
それに、会場にいたケーブルオペレーターは、わりと近隣の2社だったが、もし、新幹線や飛行機に乗ってやってきたケーブルオペレーターがいて、講演の始め5分でそんなことをいわれたら、「わざわざ、そんなことをいわれるために、出てきたわけじゃない!」と殴ってやりたい気持ちになるだろう。(そうでないと、それはそれで問題ですが…)
私は、落語が好きで、たまに上野の鈴本に行きますが、10年以上前に、落語家の誰かがいっていたのですが、落語には、「さんぼう」というのがあって、けちんぼう、つんぼう、どろぼうの話はしていいが、お客さんの職業の話はしてはいけない、という決まりがあるんだそうです。
けちんぼうは、金を払って落語などを聞きに来るわけがない。つんぼうは、今は、手話で落語をやる人もいるでしょうが、まあ、寄席に来ることはあまりないだろう。どろぼうは、まあ、客席にいても、「この野郎、オレの悪口をいいやがって」と文句をいってくることはない。だから、「さんぼう」の話はしてはいいけれど、お客さんの職業の話はしてはいけないと、固い教えがある。それを聞いて、私も、なるほど、と思いました。ですから、人前で話すときには、非常に気を遣います。
もし、あることを否定的にいわなければならない場合には、「こういういいところがあるんだけれど、こういう欠点をこうすると、もっといいと思う」というような、まわりっくどい言い方になります。
どこかに講演に行って、生きて帰ってくるためには、あるいは、主催者に迷惑を掛けないため、そして、もう一回呼んでもらうためには、やはり発言には気をつけないと、といつの間にか用心するようになりました。
今回出会った講演者は、ケーブルテレビで、働く人たちの悪口を言ってしまったと思います。本人は、そう思っていないかもしれないが、結局は、ケーブルテレビで働く人は、自分の仕事をけなされたような気持ちになるでしょう。
都会からいなかにいって、居酒屋で飲んでいて、地元でとれた山菜を出され、「こんなものしかねえのか?」といちゃもんをつけているようなものです。
そんなことを地元のコワイ人に聞かれた日にゃあ、生きて帰ってこれないってことだってある。そういう自覚がないのかなあ、と思いました。
ましてや、セミナーは、余所様の主催。ただで、自分で集めてやっているのとは違う。
セミナーの主催者というのは、そのセミナーの大小に係わらず、「自分達が企画して招いた講師の情報や考え方が、参加した人たちに伝わり、満足して気持ちよく帰ってもらいたい。そして、またたくさんの人に来てもらいたい」というのが本音です。
それを「日本のケーブルテレビは垂れ流しばかり」といわれた日にゃあ、ケーブルテレビオペレーターは、アイツの話なんか2度と聞けるかぁ、と思うのが人情というものです。
だから、講演者も、お客さんに「喜んで、気持ちよく帰ってもらって、私の話をまたぜひ聞きにきてください」という気持ちでやらなきゃいけない。ましてや、講演料もらって話しているんだから、余計だ。その金を払っているのは、参加者で、ケーブルオペレーターだって払っている。
たとえ「申し訳ないけど…」と断ろうが、悪口と思われるようなことをいっちゃいけない。いうんなら、もっと時間を掛けて、心を込めて、納得するように、うまく言え!ということです。
悪口いわれるために、セミナー代を払って、わざわざ交通費と時間をかけて、出かけてくる客がいるわけがない。
いろんな職業がある。やっぱり、それで、食っている人に対する『敬意』というものは示さなければいけない。それは、ルールです。そうだ。「敬意を欠いた発言」なんですよ。だから、腹が立つんだ。
ああ、口は災いのもと。私も、気をつけないと。(い)
【目次】
◆1.地上デジタル放送の普及促進と課題等に関する一考察
■ 地上デジタル放送の家庭への普及はこれからが正念場
■ テレビは壊れないと買い替えない
■ 放送局に迫るデジタル化投資、情報化投資
■ 景気の回復の恩恵は一部の大企業のみ
■ メディアの多様化による旧来のメディアの変革の予兆
■ 好きなコンテンツをいつでもどこでもどんな端末でも見られる時代へ
◆2. 7月25日!家電製品アドバイザリー資格試験の締め切り迫る。
◆3.となみ衛星通信テレビ㈱がRF リターンを利用したPPV サービスを開始
◆4.NECビッグローブ株式会社が誕生
◆5.テレビ・ブログ・検索サービスを横断したトレンド分析「BIGLOBE旬感ランキング」開始
◆6.世界初のネットワーク配信デジタルシネマ共同トライアル「4K Pure Cinema」
◆7.USEN、完全無料ブロードバンド放送「GyaO」にてエリア別CM 配信を開始
◆8.「CATVブロードキャスト方式緊急地震速報データ配信システム」プロトタイプ完成
| 次号へ | cbaニュース一覧 | 前号へ |