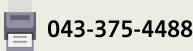cbaニュース
第271号 「NTT対抗軸を巡るケーブル囲い込みの熱き戦い」
[2007.02.18号]
ある地方の飲み屋でのこと。
「『あれは男の子がかわいそうだ』とうちのおっかあがいうんだよ。それで、オレもPTAの時に、<どの先生かな>と思ってみてみると、女の先生は少ないからすぐ<ああこの先生だな>とわかったわけよ。たしかに、おっかあのいうとおり、胸の谷間がはっきりとわかるような服を着ているわけよ。まあ、男にとっちゃあ、いくつになっても『いいもの見せてもらった』ということになるだろうけど、おっかあに聞いてみると、いつもそういう服を着ているというから、『たしかにたまにだったら、サービスということもあるだろうけど、年頃の若い男にとっては、目の毒というか、つらいものがあるかもしれないなあ』と話したんさ」とA。
Aの次女がこの高校に在学し、AはPTAの役員をしているという。
顔は想像できないが、大きく胸の開いた姿が眼前に浮かんでくる。
「たしかにウチの高校はきれいな先生が多いよ。オレ、<やっぱり来てよかったな>と思ったもの」とB。AもBも(今回の話には出てこない)CもDも、そして筆者も男子校出身者である。要は、高校の同級生なのである。2年おきに正月に十数人が集まって酒を飲む。
Bは、大学を卒業後、1、2ヶ所の高校を回って、その後母校に赴任。長いこと男子校の英語の先生を務めていた。3年ほど前に会った時に、
「もうずいぶん長いこといることになるけど、そろそろ異動になるんじゃないの? 希望なんかは聞いてもらえるの?」と尋ねると、
「うん。一応、希望は女子高に出している。まあ、共学でもいいけどね」というから、
「え~、まだ女子高の先生になる夢を捨てていないのか~?」と聞き返すと、
「先生になった時から、一度は女子高の教壇に立ってみたいというのがオレの念願なんだよ。男子校出身の先生なら、口に出さなくても、みんなそう思っているんじゃないかなあ~」と最後は真顔である。
そして、昨年、Bは、Aの次女が通うこの高校に赴任してきた。Bは、
「たしかにあの先生は露出が際立っているかもしれない」と今度は相好を崩してAの話を引き取った。筆者が、
「う~ん。近頃の高校というのはずいぶんと変わったんだなあ」と全体的な感想を漏らすと、Bがすかさず、
「いや、それぞれの高校によって全然違うよ。やっぱりトップの考え方ひとつでがらりと変わるよ」ときっぱりと言い切った。Aは、Bに酒を注ぎながら、ポツリと、
「あの先生、町外れで、若い男と一緒に暮らしているんだよな」といった。Bは、
「えっ、同棲してんの!? ウソッ!」といって絶句した。顔の赤みが一瞬消えた。何がしかのほのかな寄せる思いがあったのだろう。Aは、
「いわない方がよかったかな~」といたずらっぽく笑う。
しばらくして、Bは、落ち着きを取り戻し、静かに杯を口に運んだ。
Bのほのかな思いは、事実を前にしても、消えることはなく、種火のように静かに燃えつづけるのだろう。
2月のある日。知り合いの家でお茶を飲んでいた。次女が都立九段高校の2年生なので、何となく話題の中心がそこに行った。名門都立九段高校であるが、彼女が入学した時には、募集人員に対して合格者は、6割強が女子で、残りが男子。クラス編成は、男女ほぼ同数にしていくが、女子の数が多いので女子だけのクラスが2クラスあるという。略して、「ジョクラ」。次女も、ジョクラに入っている。母親は、
「女子高だと、男子の前に出ると、女の子っぽいところをみせる、ということがあるけれども(実は、その変化が一番コワイのだが)、共学だと、男も女も何も気にしてないから、うちの子は男っぽくなっちゃって」という。たしかに、何のくったくもないようにみえる。
「ジョクラなんて、体育の着替えの時に、男の先生がいても、さっさとブラウスを脱いでブラジャー一枚になって着替えるものだから、先生が驚いて、クルリと黒板の方を向いて、しばらくすると、『みなさん、もう着替えは終わりましたか?』と聞いているんだっていうんですよ~」と母親。
男子校出身の筆者は、<集団で先生をいじめているか、そうではないにしろからかっているのではないか>などと思ってしまう。あるいは、何のくったくもないのかもしれない。
そのうち、「都立九段高校がなくなる」というので、何のことかと思い、聞いてみると、中高一貫教育の導入により、平成17年4月に都立白鴎高校を母体にした都立白鴎高等学校付属中学校が開校し、平成18年4月には、都立両国高等学校付属中学校、都立小石川中等教育学校、都立桜修館中等教育学校が開校した。そして、都立九段高校を母体に、千代田区立九段中等教育学校も平成18年4月に開校した。「九段高校は、都立ではなく、区立になってしまった」という。
<中高一貫教育>という言葉は知っていても、その年頃の子供がいないので、現実的な感覚がなく、<中高一貫教育は現実に進展しているのだ>と初めて実感した。
そういえば、前出のAもBも高校の合併の話をしていたことを思い出した。
中高一貫教育とは別に、これから全国で、少子化による小中高等学校の整理統合、そして大学の整理統合や廃校が本格化してくるのだろう。
ある晩。日比谷の焼き鳥屋。円周率が、「3」の話になった。Tさんが、
「円周率って知ってる?」と訊くから、
「それはトンチか、クイズか?」と聞き返すと、
「いやいや真面目な話。うちの子供は、円周率「3」だもの。今度また「3.14」に戻るらしいけど。それで、いいのかなって思うよね」
一時、円周率は、「3」でよかったらしい。 やがて、杯を重ねるうちに、
「やっぱり、日本人は、<読み書きそろばん>が基本。これを小さい時にきちんとやっておけば、たいていのことは大丈夫じゃないの」と江戸時代の寺子屋システムにみんなで敬意をはらい、結局、円周率は「3」ではおかしいと問題を投げかけたTさんにみんなでご馳走になってしまった。(い)
【目次】
◆1.ジュピターテレコム2006年12月期 決算説明会抄録
―テレビへの原点回帰、多チャンネルコンテンツは量より「質」の時代へ
(株)ジュピターテレコム 代表取締役社長 森泉 知行 氏
■ 2006年12月期の連結決算の概況 ■ ケーブルテレビ各社のオペレーションの実績
■ 2007年度の基本方針 ■ 2007年通期の業績見通し
【質疑応答】
■ 地震・子供見守りサービス等への取り組み ■ KDDIとの連携は?
■ ケーブルウエストのARPU、解約率、FMCへの取り組み等
■ 今年はもう1にテレビ、2にテレビ、3にテレビで、テレビをもう一度増やす
■ M&Aについて ■ デジタルコンパクトについて
■ NGNへの取り組み ■ 300万加入達成はいつ?
■ 加入者のプロファイル ■ ARPUの目標、KDDIは脅威?
■ 多チャンネルコンテンツの質の向上
◆2.ソフトバンクテレコム、ケーブルテレビ事業者向け固定電話サービス「ケーブルライン」の提供を
開始
◆3.KDDI、クアルコムジャパン、携帯電話向け有料多チャンネル放送の市場性に関する調査結果
発表
◆4.シンクレイヤ、緊急地震速報対応「新型告知放送システム」販売開始
◆5.「Ameba(アメブロ)」が大手パソコン教室と事業提携
―団塊の世代をターゲットにブログライフ提案
◆6.「Ameba(アメブロ)」が原宿に公開録画スタジオ「Amebaスタジオ」をオープン
◆7.【ケーブルテレビ経営セミナー案内】
| 次号へ | cbaニュース一覧 | 前号へ |