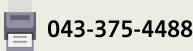cbaニュース
第333号 「つながる、つながる、みんなつながる。誰がつなげる」
[2009.11.09号]
(前号に続く)10月16日、17日の岡山理科大学大学院での集中講義は、朝の9時10分から夕方4時過ぎくらいまで、途中小一時間ほどの昼食休憩、1時間ちょっと毎の10分ほどの小休憩を挟んで延々と続く。学生も、聞いているばかりだと眠くなるだろうから、途中いろいろ質問をして、少し考えてもらったり、意見をいってもらったりする。しかし、なにせ85年の生まれであるから、85年あたりから現在までの自分たちを取り囲むメディア環境の変化を「メディアビジネスの変化とその背景」というような視点で改めて考えたことはおよそないようだ(だからこそ話をさせてもらっているのだが)。
専門の違いもあるだろう。彼らは、情報系でプログラムを普通に書く。一時熱心に「Livetube」( http://livetube.cc/ )に生中継動画の投稿をしていたという女子学生は、お世話になった方へのお礼(ここが良くわからないが、彼女なりの感謝とお礼の表現なのだろう)に、あるシステムの一部を担当してプログラムを書いていて、もう少しで出来上がる、といっていた。
筆者は、「プログラムを書く」という言葉を耳にしただけで、気持ちが一歩飛びのき、身の毛がよだつ。だから、彼らが普通に「プログラムを書く」ということだけで、大変な驚きで、思わず、尊敬してしまう。
筆者が彼らの年齢の頃は、「プログラムを書く」というだけで、先進的な分野に取り組んでいるイメージがあり、就職にしろ、はたまた恋愛にしろ、少なからず優位性があった。
そんなことを話すと、「今は、普通にプログラムが書けるのが当たり前。特に、抜きん出たプログラムが書ければ別だが、ただ書けるだけでは、就職にしても何の優位性もない」という。
「プログラム書き」でお礼を表現している最中の女子学生は、その会社の人から、「プログラムを書くのに一番重要なのはコミュニケーション。まわりのみんなやお客さんときちんとコミュニケーションを取ることができれば、プログラムを書くのは、会社に入ってからでも覚えられる」といわれたという。
どんな世界に行っても、やはりコミュニケーションが一番重要だということだろう。
それはそうだ。人間は、コミュニケーションをする生き物で、しかもその刺激によって、喜怒哀楽という感情の波動が起こり、それによって、生きるエネルギーを与えたり、得たり、失ったり、失わせたり、という所業を繰り返す。
80年代後半、「ビジュアル・コミュニケーション」ということが良くいわれた。そういったものが将来実現する、実現させるんだ、という勢いのあった頃である。
そして、その後の土地バブルの崩壊、ITバブルの崩壊があろうと、技術の革新や発展は、ビジュアル・コミュニケーションを現実のものにしている。
まだまだ使い勝手が悪かったり、多くの人に利用されているというわけではないが、やがてそれも普通のことになっていくのだろう。
今、24才の彼らも、もう20年もすると、昔のメディア環境について、母になり、父になり、子供たちに伝えていたり、あるいは仲間同士集まって、あの頃のネットのスピードは今と比べるととんでもなく遅かった、などと懐かしく思うのかもしれない。
講義とはいっても、なにしろ、彼らの親と筆者は同世代であるから、少しばかり先に生まれて親になっている者が、息子や娘にわずかばかりのうんちくを傾けているようなものだ。
例えば、「『夜のヒットスタジオ』って聞いたことない?」と聞くと、4人が4人とも、遠く虚空を見上げるような表情をして、その後、互いの顔色を窺い、「聞いたことがある……」と返ってくる。親に聞いたことがあるのか、昔のことを書き記した雑誌や書物で読んだのか、はたまたYouTubeに上がっている映像を見た誰かが、「あのタレントさあ~、若い頃ってさあ~、歌手だったんだぜ~」などと騒いでいるのを耳にしたのか。どこで聞いたのか、そこまでは突っ込んで聞かなかった。突っ込んだところで、また遠く虚空を見上げるだけだろう。
講義では、彼らの身近にいる存在という雰囲気を醸し出し、堅苦しい時間を過ごしたという感覚だけは残さないように務めている(彼らが、どう思ってくれるかはわからないが)。
彼らとの28年という年齢差の中には、世界の歴史がぎっしり詰まっており、筆者はそのほんの一部分だけを切り出して、少しばかり紹介しているだけである。
その中で、「気になる言葉や事象」があったら、彼らはためらいもなくインターネットで検索を掛けるだろう。すごい世の中になったものである。ふと気になって、「子供の頃、百科事典ってあった?」と聞くと、一人が「あった」と答えた。しかし、「使ったことはない」という。
彼らでさえそうなのであるから、今は、インターネット環境が整った家庭の小学生などは、「分からないことはネットで検索」が毎日のことになり、「百科事典など見たことない」のが当たり前になっているかもしれない。
百科事典で著名な出版社の市場も、少子化にさらに上乗せするように、縮小しているのではなかろうか。そう思って、「検索」してみると、2008年に「改定新版 世界大百科事典 全34巻」が出版されている。百科事典は、それはそれなりに、役割を持って後世に伝わっていくものなのだろう。
先祖代々続く古い家柄の家の倉庫から、国宝級の昔の文献などが見つかったりすることがたまにある。そういったこととは、全然話のグレードが違うが、もしかすると、今現在、普通の家でも、孫などが古い百科事典を開き、ページの間に挟まったままの押し花を見つける、というようなことがあるのではなかろうか。百科事典は、わからないことを調べるのにも使われたが、夏休みの宿題の押し花づくりには欠かせないものだった(と、筆者は思う)。今は、小学校で、押し花づくりなどするのだろうか。
それぞれの地域でそれぞれの草花が育つ。押し花も、押し花をつくる人の姿もとても素敵な地域コンテンツで、ケーブルテレビのエリア内にYouTube的なサイトを設けて紹介すると、コミュニティのコミュニケーションを促進するのにも役立つだろう。もちろんYouTubeに上げたっていい。今の季節なら、おばあちゃんの漬物づくりの紹介もいいかもしれない。(い)
*ちなみに、現在、So-netで放送されている「インターネット落語会」は、12月1日から、YouTubeチャンネルで流されます(現在は、移行期間中で、両方で見られる)。若い人の懐に飛び込んで(若い人が利用しているメディアに載って)、昔からの伝統芸能を後世に伝えていくということなのでしょう。大学卒のイケメンの落語家も増えていますから、これで、また寄席に若い女性客が増えることになるでしょう。落語好きにとっては、寄席の楽しみが増えるというものです。
(昔、大相撲をラジオで放送しようという計画が持ち上がった時、猛反対の声が上がった。理由は、客が来なくなるからだった。しかし、ラジオ放送を始めると、お客は増加した。戦後、テレビ放送が始まり、大相撲をテレビ中継しようという計画が持ち上がった。さすがに「映像」を見せてしまったら、お客さんは来なくなるだろう、ということで、ラジオ放送の時と同様に反対の声が上がった。しかし、実際にふたを開けてみると、お客さんの数は増えていった。生の迫力を伝え聞いた人々が、一度は足を運んでみたいと思うからだ。
メディアに載ることで、集客効果があるというのは、野球やサッカーでも証明されていることで、落語のような芸能も、メディアに載ることで、集客効果や伝統文化の継承が促進されることが期待される。
これまでのテレビでは、放送時間枠を取ること自体が難しかった。しかし、ブロードバンド時代を迎え、これまでなかなかマスコミに登場する機会が少なかった様々なスポーツやイベントの動画情報が、興味のある方々の下に、オンデマンドで届くようになってきた。
一方、テレビの魅力は、やっぱり「生」だろう。駅伝にしろ、ナビスコカップにしろ、日本シリーズにしろ、ワールドシリーズにしろ、ついつい腰を落ち着けてしまう。松井バンザイ!!ああ、今日の巨人―日ハム戦も見逃せない。) 11月5日
【目次】
◆1.CEATEC2009開催《フォト・レポート》
◆2.グッドコミュニケーションズとメディアキャスト、ユビキタス特区で
ホテル内デジタルサイネージ実験を実施
~ データ放送機能を駆使し、客室のテレビへ地域情報を配信 ~
◆3.仙台CATV、KDDIとの提携により固定電話サービス開始
◆4.ニューメディア新潟センター、KDDIとの提携により固定電話サービス開始
◆5.KDDI、「ひかりone」TVサービスの料金を改定
―より安価での利用が可能に
◆6.「KDDI ペーパーレスFAXサービス」提供開始に
◆7.KDDI、NECがデジタルサイネージの活用に関する共同実験
◆8.ユビキタス特区における携帯端末向けマルチメディア放送サービス実証試験実施
◆9.出雲ケーブルビジョンJC-data を利用した地域コミュニティデータ放送サービスを開始!
~地域密着情報をデータ連携システム「とりこみ君」を使って自動表示~
◆10.GMO マーケティング株式会社とジャパン ケーブルキャスト株式会社が協業
成果報酬型の新しいクロスメディアマーケティングソリューションサービスを展開
◆11.「ひかりTV」テレビサービスのチャンネルラインナップ拡充
~本邦初チャンネルが10チャンネル!ハイビジョンチャンネルが32チャンネルに!~
◆12.映像配信サービス「ひかりTV」における地上デジタル放送IP再送信の提供エリアが
北海道に拡大
◆13.家電・オフィス機器などをネットワークにつなぐことでより豊かで便利な暮らしを
実現するトライアルを開始
~ホームICT基盤のテストベッド環境上でのサービス創造に向け協業の推進~
◆14.経済的な理由で地上デジタル放送がまだ受信できない世帯への簡易チューナー給付支援の
申込み状況(10月31日現在)
◆15.日本ケーブルテレビ連盟が、携帯端末向けマルチメディア放送の導入に伴う
混信対策検討ワ-キンググループの設置を検討
◆16.NHK放送研修センター「研修案内」
◎放送人必須セミナー~放送と人権・放送と表現」
| 次号へ | cbaニュース一覧 | 前号へ |