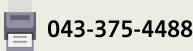cbaニュース
第336号 「鳩山首相がツイッターを始めてフォロワー登録が増加」
[2010.01.06号]
12月1日から、落語協会の「インターネット落語会」が、それまでのSo-netからYouTubeに引越しをした。理由はわからないが、11月は、移行期間で、12月1日からYouTubeで正式に放送されるようになった。画角は、横長になったがPCの画面上に映るスペースは、一回り以上、小さくなった。しかし、まあ、好きな落語が手軽に聴けるのであるから文句はない。
常日頃は、テレビを視聴している。(基本的にNHKだが)朝のニュース番組などは、つけっぱなしにしているし、ややもするとそのあとの料理番組なども、今夜のお酒のおつまみにどうか、などと見てしまうこともある。
その後、取材等で出掛けることもあるし、そうでない時には、自室で原稿を書くことになる。もちろんすぐに頭が全開するわけはないので、メールチェックやその返事を書いたりで小一時間ほどは経ってしまう。これは、おそらく誰にでも共通する朝のお決まりの作業であろう。そのあと、ベッキーのデジ川柳をチェックして、仕事に取り掛かる。http://digisen.jp/pc/
最近、生テレビを見るのは、お昼のNHKスタジオパークや夕方のニュース、スポーツくらいで、ドラマやドキュメンタリー、映画にしても、みんなHDD録画して、タイムシフト視聴になっている。もう250Gでは足らなくて、過去の残しておきたい映像をなくなく消しながら、「3時間ほどの残り時間」を搾り出して、使い回ししている。お正月を前に、250Gをあきらめて、ブルーレイ内蔵のSTBが地元のケーブル局から提供されるようになったら、取り替えようと決意した。250Gの中には、北京オリンピックの上野由岐子選手の力投の映像も入っているが、あきらめることにした。ディーガを買ってムーブして、その後またブルーレイ内蔵STBをケーブル局からレンタルしたり、買ったりするだけの余裕はない。
11月の半ばくらいの深夜、録画した落語番組も見てしまい、YouTubeのインターネット落語会もすでに見てしまっていたので、久しぶりにJCNのVODサービスのボタンを押してみた。その夜は、「職人魂」という番組にはまって、何本も見てしまった。〈職人と呼ばれる人は、ここまでやるのか〉と、その技に驚かされるまま、次から次へとボタンを押した。
次の夜も「職人魂」の続きを見て、その次の夜は、噺家で切り絵師の柳家松太郎(しょうたろう)が案内する「~街角散策~駅からマップ」という番組を何本も見た。身近な「駅名」がどんどん出てくるから、ついつい引きずりこまれて見てしまう。オンエア時には、見ていないが、こうした地域情報番組をVODで、まとめて好きなだけ、たっぷり見られるからありがたい。
もしかすると、実際に行ってみると、〈な~んだ、こんなところか〉と思うのかも知れないが、それでも、〈ここが、コミチャンで取り上げていたところか〉という感慨があるだろう(残念ながら、まだ実際に散策には足を運んではいませんが)。
年末のある忘年会で、JCN関係者に「地域情報番組をVODで楽しんでいる」と伝えたら、「無料のコンテンツ視聴は伸びているんですが、有料の方も伸びてくれないと」といっていた。現場で、事業としてサービスを提供する方の気持ちとしては、そうだろう。しかし、筆者からいわせれば、そもそもVODは、双方向の映像配信のシステムであって、それが生活の中に視聴習慣として定着するかどうかの方が先である。映画やドラマのコンテンツ配信と課金のシステムであるというのは、その次に来ることだ。ましてや、VODが、「パッケージのビデオレンタル事業に代替するような映画やドラマのコンテンツ配信と課金のシステムになりうる可能性を秘めている可能性がある」というのは、また違う次元の話となるだろう。
『VODで映画を流せば儲かる』という単純な図式でVODをとらえるのは、たいへんな勘違いで、わが国のコアな映画人口が、アバウトで200万から300万、年に何度か映画館に行くという層を含めても、映画人口2000万ほどといわれている中で、映画やドラマのコンテンツをVODに用意したくらいでは、利用者は増えないし、儲からない。
しかし、流れとしては、用意しておかなければならない。筆者が、VODに出会ったのは、もうかれこれ27年ほど前。奈良の生駒のHi-OVIS実験で初めて体験した。それから、VODの時代が来るといい続け、ようやくそのサービスを手に入れた感激は一入である。しかし、たいてい、一般の方にとっては、『何のこっちゃ』である。視聴習慣が根付かなかったら、お金を払っても、という次のステップには進まない。したがって、ケーブルテレビのVODシステムは、本来、無料の地域コンテンツが繰り返し視聴されることがきわめて重要で、その視聴スタイルの変化の中で、運用費用などを地域広告でまかなえないか、というあたりがビジネスとしての入り口になるのではないだろうか。VODの視聴習慣の広がりの中で、お金を払っても視聴する層が醸成されてくる。だから、無料にしろアクセスが増えているということは、いい傾向なのである。J:COMのある方も、VODの無料の地域コンテンツはかなり見られているといっていた。
ある夜、BS2で放送された関西の落語番組をHDD視聴した。翌日昼間、昼食後の腹ごなしに、テレビを見ていたが、面白くなく、VODボタンを押した。メニューを順に見ていくと、「NHKオンデマンド」の文字が目に飛び込んできた。どうなっているのかと、順に進んでいき、落語を選択すると、BS2のマークがあった。〈これはもしかすると、この間、放送したもの?〉とそれを確認したくなり、ついボタンを押してしまった。〈あっ!〉と気が付いたのは、その直後。「315円」の文字が目に入ってきた。当然、同じ番組で、まあ好きな落語なので、1時間視聴した。その後、仕事を始めたが、原稿書きの合間に、気分転換に、ネットで「鈴本演芸場」を検索すると、12月21日から28日まで、年末特別企画のお笑い師走会が開催されている。
順に、出演者を見ていくと、関東と上方の女性落語家4人が登場する「東西女流競艶」と銘打った23日の夜の部には、わが家で人気の桂あやめさんが登場する。よく見ると、昼の部にも出演する。大阪に行く機会があったら、ぜひ天満繁盛亭に行ってみたい、そこで桂あやめさんの高座を生で見てみたい、と願っていたから、たいへんに嬉しい情報に出会ったことになる。 それから仕事に巻きを入れ、23日は、早起きをして、上野鈴本演芸場に出掛け、昼の部から夜の部まで、たっぷりと落語三昧の1日を送った。何でもそうでしょうが、やっぱり、生は迫力が違いますね。(い)
【目次】
◆1.巻頭言 「2010年は、地上デジタル放送完全移行に向けた勝負の年」
◆2.CGMマーケティングとRSS広告社、バナー上からTwitterのツイートを
投稿できる「Tweetbanner Post」を開発
◆3.東京ケーブルネットワーク、KDDIとの提携により固定電話サービス開始
◆4.CAC、KDDIとの提携により固定電話サービス開始
◆5.JCNが、株式会社ケーブルテレビ足立の株式を取得
◆6.イッツ・コム、東急エージェンシーが、渋谷駅周辺における地域情報配信の手段として
エリアワンセグの実証実験開始―約1年間にわたって、サービス実用性を検証
◆7.光ファイバーを利用した放送サービス「MEGA EGG 光テレビ by HICAT」を提供開始
~平成21年12月22日から受付,平成22年1月12日からサービス開始~
◆8.鳥取県のケーブルテレビ局4局にRF常時監視サービスの提供を開始
~県内の放送のフルデジタル化を見据え、各局連携して監視体制を強化~
◆9.株式会社ジュピターテレコム 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 森泉知行
2010年 社長年頭所感(要旨)
◆10.TikiTiki インターネットで、衛星ブロードバンドサービスを開始
◆11.TikiTikiインターネットで、WiMAXサービスを開始
-下り最大40Mbpsの高速モバイル
◆12.テレビの大画面で観る、最高品質の映画予告編&ランキング番組
-日本初、ネット・サービス映画情報番組「myシアー」、アクトビラでスタート!
◆13.NHK放送研修センター「研修案内」
◎「災害にどう対処するのか」~ケーブルテレビの緊急災害放送~
| 次号へ | cbaニュース一覧 | 前号へ |