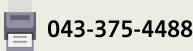cbaニュース
第252号 「米国でも光ビデオサービスの競争環境の整備進む」
[2006.05.03号]
某月某日。某所。某セミナー。開演前に、某先生のプレゼンテーション資料をみると、「日本のケーブルTVは、未だに電話の対抗産業にまで成長していない」という一文があった。(どういう分析を加えるのだろう)と期待した。講演でも、そう話し、加えて、かつそれは、「コンテンツが面白くないから、ケーブルにはいらないからだ」という解説をつけた。(すごい理屈。こんなの近頃聞いたことがない話だなあ)と驚いた。続けて、「日本の放送業界は、保守的であり、起業家精神がない」とレジメにも書いてあり、そう話した。(そうかなあ。この人、放送業界にケンカを売ってるのかなあ)と思った。その後、ディスカッションに移り、別の某先生は、何かの拍子に、「日本のケーブルテレビは普及していない」とボソッといった。(アレレ、この人もおかしいぞ。おいおい、FACTデータも示さずに、本当にそんなこと言い切っていいのかあ?)と思った。会場にいる人は熱心に話に聞き入っている。(事実と違う情報を聴衆に流しては、まずかろう。しかも、中には、証券アナリストもいるらしいし)と客席、プレス席なので、前から2列目、でだんだん腹がたってきた。それが事実なら、別にいいんですが…。
でも、人を信用させるに足る、名のある先生が、誤情報(誤情報と認識していなかったらますますコワイ)を流すということは、とてもいけないことです。それを信用した人は、間違った情報で、動いてしまって、たいへんな損害を受けたり、または、人に損害を与えてしまうことだってありえます。風評被害のもと。
それに、この間、永田議員の偽メール事件があったばかり。エビデンスをきっちり出さずに、ある業界を批判するというのは、きわめて、キケンなこと。
日本の放送文化に、それなりの敬意を払い、事実を列挙した上で、批判をするのはわかりますが、それなしで、「斬り捨て」では、議論ではない。しかも、それで、会場の聴衆を信用させてしまうのは始末が悪い。というか日本人は素直だから偉い先生の言はすぐに信用してしまう。
2時50分頃、第一部の終了間際に、質問のコーナーができたので、すかさず、マイクをとり、某先生に、「ケーブルテレビが電話の対抗産業にまで成長していない、というのは、ある意味で、事実かもしれない。しかし、80年代前半に、都市型ケーブルテレビができるときに、政策的に、小さなエリアに限定されたわけで、そのことを考えれば、少なくとも『成長してきている』と思いますが」というと、会場からは、何か、<先生に文句つけるなんて、なんなんだあいつは>みたいな大きなムードが押し寄せてきた。
一瞬後を振り返り、「逃げ道確保」の確認をいたしました。取り囲まれるのイヤだから。(いいや、電話のことをいって、わざわざ、ケーブル業界の事情を教えてやる必要もあるまい)と思い、電話の話はやめましたが、先生は、ケーブル業界が、電話サービスを行なっていることをご存知ないような回答でした。
次に、「コンテンツが面白くないからケーブルにはいらない、と、先生が先生の立場で発言することは、非常に危険な発言だ」と伝えました。「コンテンツが面白くないから、ケーブルにはいらない、というのでしたら、現在、NTTがFTTHの普及のために、映像サービスの売込みをしていますが、このコンテンツはケーブルに流しているものとだいだい同じ物が多いわけでして、コンテンツが面白くないから、ケーブルにはいらないのなら、コンテンツが面白くないから、FTTHにも入らない、ということもいえるわけで、そういう結論になるのは、まずいのではありませんか?」と聞くと、「確かに、コンテンツが面白いかどうかは、個人の問題だ」と。
次に、「地上波のテレビ局が、起業家精神がない、といいましたが、もともと免許をもらってやっている事業であり、郵政省の管轄下で、事業を行ってきたわけですから、これからはどうかわかりませんが、起業家精神がない、と決め付けるのはいかがなものかと思います」といいますと、「まあそれは確かにその~」みたいな感じでした。
次に、別の先生に、「先ほど、日本のケーブルテレビは普及していない、と発言されましたが、その根拠はなんですか?」と聞くと、後半が聞けなかったのか、あるいは、「根拠はなにか?」と聞くなんてなんなんだコイツ、と思ったのかわかりませんが、「なんていったんですか?」と聞き返すので、「根拠はなんですか?」と聞きました、というと、黙ってしまったので、「日本ではケーブルテレビの多チャンネルが約600万世帯、接続世帯数は1800万世帯、ビル陰などの小さな施設をあわせると、51%程度の世帯が、ケーブルテレビでテレビを視聴しているという現状があるわけで、したがいまして、私は、『ケーブルテレビが普及していない』とはいえないと思います」というと、憮然とした表情をしていました。
その夜は、怒りで、よく眠れませんでした。ケーブルテレビがどうのこうのではなく、両先生ともテーマとして扱う日本のケーブルテレビの現状について、下調べをしていない。(だろう。そうとしか思えない)
これは、テーマがケーブルテレビであろうとなんであろうと、同じであって、根拠をださないというのは、おかしい。しかも、はなはだしい、誤認。これで、日本人は、偉い人がいうと、みんなすぐ信用するから、「風評被害」がおきる。というところで、非常に怒りました。
それにしても、「ケーブルテレビは電話をやっていない」というのは極めて異例の事実誤認。総務省のHPにいけば、普及データがあるのに。(い)
【目次】
◆1. 米国通信市場の再編。ベル系地域電話会社(SBC、Verizon)が長距離電話会社(旧AT&T、
MCI)を買収―ケーブルテレビとのビデオサービス競争の幕開け(講演抄録)
講演1.「米国の通信政策の方向転換」
講演2.「束縛から開放された革新、投資、そして競争」
◆2. STNet『ピカラ光でんわ』の申込者数が1万件突破!!
◆3. 女子美術大学・長野県高山村・須高ケーブルテレビ株式会社が連携事業で村づくり
◆4. 横浜のケーブル局4社合同でハードディスク内蔵型STB「HitPot」を導入
~2番組のハイビジョン放送が簡単に楽しめるSTBを採用~
◆5. 中部ケーブル、シーテックが5月よりVODサービス開始
◆6. 仙台CATV㈱がRF リターンを利用したPPV サービスを開始
~双方向サービスの充実により更なる高付加価値サービスを展開~
◆7. 5月9日、デジタルハリウッド主催、クアルコム共催、KDDI特別協賛による
BREW® JAPAN Conference 2006を開催
◆8. スターキャット新社長に、加藤篤次氏が就任
| 次号へ | cbaニュース一覧 | 前号へ |