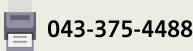cbaニュース
第347号 「多様化を見せ始めたケーブルテレビのビッグベーシック」
[2010.05.10号]
前号の送付状で、「ベッキーのデジ川柳」のコメント機能が加わったことで、川柳の投稿者同士のコミュニケーションがたいへんに進んだ、と紹介した。
コメント機能を正確に紹介すると、自分が投稿した川柳にコメントが寄せられ、コメントをくれた方に返事をするには、相手が投稿した川柳を見つけて、そこからコメントを返すことになる。したがって、しばらく相手が投稿して来ないと、日にちを遡って、相手の川柳を探すということもある。その探す間に、いろいろな方の川柳に目を通すことになるから、けっこう遊べるのである。
この「コメント機能」の本質は、『鏡』だと思う。コメントが返ってくることで、相手という鏡に映った自分が見える。そして、自己の存在を確認できる。サイトを開いて、コメントが来ていると、「未読コメントがあります」と、表示される。その瞬間、誰もが喜びを感じている(筆者自身も)。その喜びは、コメントの中に表現されている。「今や、誰もが情報(コンテンツ)の作り手であり、情報(コンテンツ)の消費者である」ことを再認識させるコメント機能である。
昔から、「番組の感想をお寄せ下さい」というのは、定番は「葉書」である。そして、これも本質は、鏡である。テレビやラジオばかりでなく、本や漫画の読者の感想も葉書で寄せられた。現在放送中のNHKの連ドラ「ゲゲゲの女房」の最近のシーンを見ても、読者の感想は、葉書で寄せられている。感極まった方は封書で思いを綴って来る。
この時代は、それしか手段がなかったが、その後、ラジオの世界では、「電話リクエスト」が、リスナーとの双方向コミュニケーションの手段として登場した。
ラジオのDJと会話する自分の声が、ラジオを通して流れてきて、それを回りのみんなも聞くことができ、その後自分の好きな曲が放送される、というキラーコンテンツであった。これはもちろん、電話というコミュニケーションインフラが普及していることを背景にしてこそ成り立ったものである。ついでにいうと、ラジオというメディアの存在感も今より高かったということである。
それから、家庭にFAXが普及すると、テレビでもラジオでも「FAXによる」意見や感想の募集が始まった。これは、もちろん今でも続いている。オリンピックの応援などの際に、放送局に届いたイラスト入りのFAXが、テレビの画面に映し出されたら、送った本人は、手元にあるオリジナルを見ながら、飛び上がって狂喜乱舞するであろう。
しかし、この喜びは、極めて少数の方たちだけのものである。
世の中に、インターネットが登場し、世界はある意味で、フラットになった。
判り易いところでいうと、YouTubeがその最大の例で、違法性のある映像が投稿される可能性があるという問題は残るが、世界の多くの方々が映像を投稿し、世界の多くの方々がその映像を視聴できるというシステムが出来上がった。
インターネットというコミュニケーションインフラが世界に普及したお陰で、日本からも、よくこの映像を録画していたなと思うような「お宝」映像が世界に向けて紹介された。「面白い映像がある」という話は、パソコンや携帯電話で、瞬時に多数の人に広まる。
いまや、消費者の行動は、「AIDMA」から「AISAS」を超えて、「ASKA」(A:アテンション・注意喚起、S:サーチ・調査、K:口コミ、A:アクション・購買行動など)の時代である。
若い方の間では、今晩見たドラマの話を、明日、学校や職場に行って、「昨日、あれ見た?」なんて悠長な会話は行われていない。その場で、携帯電話で、友だちにメールして、感想や意見を言い合っている。そして、その思いは、その場で完結してしまっているのである。
何らかのコンテンツから刺激(外部刺激)を受け、その感想を携帯電話で友人に送り、意見をやり取りして、時間と感情を共有しているのである。
いわば、太陽の光を手鏡で受けて、その光を遠方の友人に送り、また友人から光が返ってくる、という様である。「ひみつのアッコちゃん」のコンパクトをみんなが持って、いつもピカピカ、コミュニケーションを繰り返しているのである。(注:アッコちゃんのコンパクトは、「返信」ではなく『変身』するものですが)
「情報(コンテンツ)を作り、情報(コンテンツ)を消費する」ということを相互に繰り返している。
NHKの「ケータイ大喜利」も人気が高いが、みんな投稿することで番組に参加することを楽しんでいる。
動画再生中に、リアルタイムでコメントが付けられる若者に人気のニコニコ動画というサービスがある。筆者は、とてもではないが感覚についていけないが、若い方は、どんどん書き込みを行っているようだ。以前、運営する㈱ニワンゴの杉本誠司社長の講演を伺った際に、「若者は、自分の映像や、書き込んだコメントに反応があることで、自己の存在を感じているようなところがある」と話されていた記憶がある。
信号を送って、返ってくる何らかの信号で、自己の存在を確認するというのは、コミュニケーションの手法は違っても、これは人間の本質的なものの一つであろう。
ブロードバンド環境の整備の進展、パソコンの普及、携帯電話、スマートフォンなどモバイルメディアの進化と普及により、そういったコミュニケーションが24時間可能になっている。ツイッター(twitter)もその一つであろう。
総務省の通信利用動向調査によれば、60代以上の年代の高い層でもブロードバンド の利用が広がっているという。デジ川柳の投稿者のみなさんの中にも、該当する方々がいる。
(cbaニュース345号で紹介した)日本ケーブルテレビ連盟の「全国ふるさとコンテンツ事業」の記者会見に参加しながら、筆者は、この「コメント機能」を思い出していた。
この事業は、「け~ぶるにっぽん-仕事人列伝-」という番組タイトルで、12のケーブルテレビ局の制作で地域の仕事人を紹介するものだ。7月から9月にかけて、全国のケーブルテレビ局のコミュニティ放送で流される。
この「全国ふるさとコンテンツ」を視聴したみなさんからの意見や感想を受け付けるのは、もはや葉書や封書ではないだろう、と思う。携帯電話のメールかパソコンであろう。
したがって、ホームページを立ち上げて、12の制作番組のあらすじやメーキングの様子、制作者のコメントなどを短い動画で紹介しながら、その中に、番組を見た視聴者が意見や感想を投稿できる掲示板スペースを設けたらどうだろうと思う。
テレビ好きな年代の高い層が、サイトに遊びにきて、しばらく遊んで、足跡を残して帰る、というような楽しい仕掛けが出来ないものだろうか。定番でいえば、クイズ。○○県出身の有名な人とか、地名の呼び方とか、有名な郷土料理とか、いろいろあるだろう。
番組を見て、「面白かった」「感動した」「もうちょっと詳しく紹介して欲しかった」「思わず食べたくなりました」「今度の休みに行ってみます」など、様々な意見や感想が寄せられたら、作り手の励みにもなるし、番組に登場したみなさんにも良いことだと思う。口コミで、広がることも期待できる。
全国で番組を見ている視聴者が、自宅のパソコンや携帯電話から、意見を言えるという参加性が、結局は、楽しい時間を提供することにつながり、ある意味、オールケーブルならではの「Webサービス」となるのではなかろうか。
(cbaニュース346号で紹介したように)日本デジタル配信(JDS)が、4月26日よりCable Gateの商用サービスを開始したが、このウィンドウを使っての「全国ふるさとコンテンツ」のPRも効果が期待できよう。もっというと、各ケーブルテレビ局が近隣のイベント情報の紹介等を携帯電話やモバイル端末を利用して行うことも、地域視聴者との接触率を高め、存在感をアピールするのに、効果があるだろう。(い)
【目次】
◆1.ジュピターテレコム、第2四半期以降の重点施策
◆2.日本ケーブルテレビ連盟、「光の道構想」に関する見解を発表
◆3.横浜ケーブルビジョンが「YCVコミュニティチャンネル」の緊急情報、安全安心情報を拡充
◆4.ケーブルキャスト、チャンネル700 で「コミュニティチャンネル向け番組供給サービス」開始!
◆5.株式会社ひろしまケーブルテレビがJC-HITS 地上配信サービスを利用したHD サービス開始!
◆6.NTTインターコミュニケーション・センター(ICC)常設展「オープン・スペース2010」開催について
◆7.NTTソルマーレ、新條まゆ監修、人気声優が読む
「声つきケータイマンガ! 声マン」を独占先行配信!!
◆8.シーエー・モバイル、振ってニュースが読めるiPhone/iPod touch用無料ニュースアプリ
ケーション「TheNewsCafe」を公開
毎日100本以上のニュース記事を配信
◆9.NHK放送研修センター「ケーブルテレビ研修」案内
| 次号へ | cbaニュース一覧 | 前号へ |